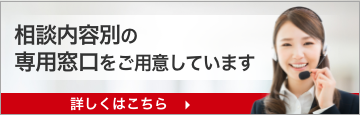【後編】辞めさせたい社員に穏便に辞めてもらう方法と、解雇の注意点とは?
- 労働問題
- 辞めさせたい
- 社員

辞めさせたい社員がいたとしても、特別な理由がなければすぐに辞めさせることはできません。前編では、解雇に必要な法的な条件について説明しました。
後半は、引き続き金沢オフィスの弁護士が、解雇の前に試みるべきことや解雇予告のルールについて解説します。
3、解雇の前に試みるべきこと
解雇とは、あくまで最終手段です。後述する即日解雇に該当する場合でもないかぎり、解雇の妥当性をめぐり社員と裁判などの紛争に至った場合は、解雇の社会的相当性を主張するために以下のプロセスを経ておく必要があります。
-
(1)暴言を吐いたり、暴力をふるう
素行不良の社員に対して、注意指導をすることを躊躇してしまう管理監督者も存在するようです。これは注意指導しても効果はないという諦念、あるいは注意指導に対して当該社員がパワーハラスメントなどと反発してくることや職場の雰囲気が悪くなるなどのことを警戒していることが理由と考えられます。
しかし、社員の処分の前段階として、注意指導は必要不可欠です。注意指導は、口頭で何回も辛抱強く行うことから始めます。それでも改まらない場合に、メールや書面により注意指導を行うことは証拠を残すために有効と考えられます。 -
(2)始末書や誓約書を提出させる
社員に始末書や誓約書などを提出させることは、当該社員の将来を戒め今後の改善を促す目的があります。それと同時に、問題行動の事実について当該社員自身が認めたことを証するうえで有用です。
-
(3)配置転換を行う
たとえば営業成績が著しく不良な社員を、総務系などの部署に配置転換させ営業現場から出すことは、営業現場におけるこれ以上の生産性低下を阻止することに有用です。また、会社が社員の雇用維持のために他の適正な部署を探すという努力を行なっていたという相当性を補完することにもなります。
-
(4)懲戒処分を行う
後述する退職勧奨や解雇以外の懲戒処分は、譴責・降格・減給・出勤停止などが考えられます。いずれも裁判など後日のトラブルに備えるため、社員の行状については就業規則や各種法令などに照らし相応程度であることを考慮しておく必要があります。同時に、処分に至る経緯や判断した理由は、必ず記録に残しておいてください。
-
(5)退職勧奨をする
退職勧奨とは、会社が労働者に対して「会社を辞めたらいかがですか?」などと勧め、社員が自発的に退職するように促すことです。
退職勧奨は会社と社員による「合意退職」を目指すものです。そして、合意退職の外見的な形式は社員の「自己都合退職」にあたります。もし退職勧奨を穏便に進めたい場合は、希望退職のように退職金の割り増しや再就職先支援など、ある程度社員に歩み寄った条件を提示する方法もあるでしょう。しかし、それが当該社員や会社全体のモラルハザード(倫理観の欠如)を助長することにならないように、配慮が必要です。
なお、あまりにも執拗な退職勧奨は「退職強要」とみなされ、強要罪や脅迫罪に該当し慰謝料や損害賠償請求の対象になることもありますので、控えるべきです。
4、解雇の種類と条件とは?
上記のプロセスを経ても社員に改善が望めない場合は、いよいよ解雇を検討することになります。
会社など使用者には、必要に応じて社員を解雇できる「解雇権」が認められています。しかし、解雇権の行使には労働基準法や労働契約法などにおいて厳しい適用基準が定められています。そして、この適用基準を逸脱した解雇は使用者による「解雇権の濫用」とされ、解雇そのものが無効になる場合もあるのです。
仮に解雇の要件が就業規則や労働契約書に明示されていたとしても、それが「客観的合理性又は社会的相当性を欠く場合は解雇権の濫用として無効」という解雇権濫用の法理に反するものであれば、同様です。
解雇には、以下の3種類があります。
-
(1)整理解雇
会社の経営が悪化したなど正当な理由がある場合に、労働者の数を削減するための解雇です。日本では、整理解雇を「リストラ」と呼ぶケースが多いようです。
-
(2)普通解雇
整理解雇や懲戒解雇に該当しない解雇です。社員の勤務成績や勤務態度が極めて悪く注意しても改善の見込みがない場合、病気のため長期にわたり職場復帰が見込めないなど、労働契約の継続が困難と判断される場合に適用されます。
-
(3)懲戒解雇
著しい就業規則違反や犯罪行為などにより、会社や顧客さらには第三者へ損害を与えたと認められる場合などに、会社が一方的に行う解雇です。
懲戒解雇の要件は、就業規則や労働契約書に具体的に明示されている必要があります。また、懲戒解雇の要件が以下に列挙する「労働者の責に帰すべき事由」に該当する場合、会社は労働基準監督署長の認定(除外認定)を受けることで後述する解雇予告の手続きを経ずして社員を即時解雇とすることができます。- 事業場内における窃盗、横領、傷害など刑法犯に該当する行為
- 賭博や風紀紊乱(びんらん)等により職場規律を乱し、他の社員に悪影響をおよぼすこと
- 採用時の不採用となるような経歴詐称
- 他の事業への転職
- 2週間無断欠勤し、さらに出勤の督促にも応じない場合
- 出勤不良について、数回にわたり注意を受けても改めない場合
なお、退職に応じなければ懲戒解雇するというような「諭旨解雇」についても、懲戒解雇の一形態と解することができる。
5、解雇予告するときのルールとは?
労働基準法第20条では、解雇を行う会社は原則として解雇する日の30日前までに社員に対して解雇予告を行わなくてはならないと定められています。
また、解雇予告を行わずに即時解雇する場合は、会社は最低30日分の平均賃金を解雇予告手当てとして労働者に支払う必要があります。この解雇予告手当ては、原則として解雇と同時に支払う必要があります。予告の日数は支払った平均賃金の日数分短縮することができます。もっとも解雇予告手当を支払ったからといって当然に解雇が有効になるものではありません。
なお、懲戒解雇の場合であっても、所轄の労働基準監督署長から「解雇予告除外認定」を受けていないかぎり、上記の解雇予告に関するルールは適用されます。ただし、解雇予告除外認定を受けていない中で即時解雇した場合でも、それが「労働者の責に帰すべき事由」によるものであれば、判例でも解雇は有効とされています(平成14年1月31日東京地裁判決)。
6、まとめ
辞めさせたい社員がいても解雇は簡単にできず、そのためには事前のプロセスが重要であることを解説しました。即時解雇できる場合にでも該当しないかぎり、社員を辞めさせることは会社として法的リスクを抱えることにつながることをご理解いただけたかと思います。
したがって、辞めさせたい社員への対応は弁護士と相談しながら進めていくことをおすすめします。社員との問題について会社側の立場から解決した実績のある弁護士であれば、会社の法的リスクを最小化しながら問題を解決することが期待できます。
このような問題にかぎらず、ベリーベスト法律事務所ではワンストップで対応可能な顧問弁護士サービスを提供しています。万が一に備えた就業規則の作成など、ぜひお気軽に、ベリーベスト法律事務所 金沢オフィスにご相談ください。
>前編はこちら
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています