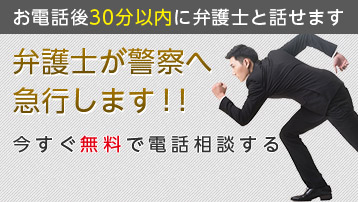飲酒運転による逮捕や罰則について解説。事故がなくても逮捕されるの?
- 交通事故・交通違反
- 飲酒運転

平成30年4月、金沢西署は、飲酒運転の疑いで北陸朝日放送の委託カメラマンの男を逮捕しました。現場の交差点で乗用車と衝突し、警察官による検査の結果、基準値を超えるアルコールが検知されたようです。
幸いにもケガ人はいなかったようですが、飲酒運転による死傷事故は数多く発生しています。「つい出来心で」「少しくらいなら」では許されないことは周知の事実だといえるでしょう。
本記事では、飲酒運転をしてしまったことがある方に向け、飲酒運転の処分内容や逮捕の有無について金沢オフィスの弁護士が解説します。
1、飲酒運転とは
飲酒運転には大きく「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の二つが含まれると解釈されています。
酒気帯び運転は「呼気1l中に0.15mg以上、血中1ml中に0.3mg以上」と、アルコール濃度の明確な基準があります。
酒酔い運転とは、アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転のことをいいます。酒気帯び運転のような具体的な数字の基準はありません。言い換えると、酒気帯び運転の基準に達していなくても、酒に弱い人であれば酒酔い運転に該当するケースがあるということです。
酒に酔った状態は非常に危険であることから、酒気帯び運転と比べてさらに厳しい処分となります。
2、どれくらい飲むとアルコール検出されるのか?
酒を1滴でも飲んだら車を運転するべきではないと分かっていても「このくらいの量なら大丈夫」と考えてしまう人がいます。飲酒と体内アルコール濃度の関係は、酒の種類や量、飲んだ人の体格、代謝、性別などさまざまな条件によって変わります。
ビール中びん1本、焼酎0.6合を飲んだだけでも、呼気中のアルコール濃度は0.1~0.2mgになるといわれています。体重60kgの成人男性が同量のアルコールを分解するまでには3~4時間はかかるようです。
近年は市販のアルコールチェッカーなどを用いて自分でアルコール濃度を測定する人がいます。しかし、測定結果は必ずしも正確なものとはいえず、そもそもメーカー側も運転可能か判断するために使わないように警告しています。
チェッカーに頼って運転の可否を判断することはリスクがあり、万が一飲酒運転になっても、それは自己責任だといわざるをえないでしょう。
3、飲酒運転をしたときの処分内容
飲酒運転とひとくちにいっても、誰がどのような状態で運転をしたのか、事故はあったのかによっても処分内容が異なります。
-
(1)飲酒運転で事故を起こさなかった場合
飲酒運転は、事故がなかったとしても、刑事責任に問われます。
罰則は次のとおりです。- 酒酔い運転……5年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 酒気帯び運転……3年以下の懲役または50万円以下の罰金
初犯の場合には、罰金刑でとどまることもあるようです。ただし、飲酒運転に対する厳罰化の流れを考慮すると、罰金刑で済むとは言い切れません。
特に酒酔い運転の場合は懲役刑を求刑されることもあり得ます。
行政処分は次のとおりです。- 酒酔い運転……基礎点数35点(無条件で免許取り消し)、欠格期間3年
- 酒気帯び運転(呼気1l中アルコール濃度0.25mg以上)……基礎点数25点(無条件で免許取り消し)、欠格期間2年
- 酒気帯び運転(呼気1l中アルコール濃度0.15mg以上0.25mg未満)……基礎点数13点(90日間の免許停止)
-
(2)同乗者がいる場合
飲酒運転をした本人だけでなく、運転者が飲酒していることを知りながら、車両を運転して自己を運送することの要求や依頼をして飲酒運転の車両に同乗した者も飲酒運転同乗罪という罪に問われます。
- 酒酔い運転の同乗者……3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 酒気帯び運転の同乗者……2年以下の懲役または30万円以下の罰金
また、このような同乗者にも行政処分があり、運転者と同様に免許取り消しや免許停止処分となることがあります。
飲酒運転同乗罪に問われた場合は運転者の飲酒を知っていたかどうかが問題となりますが、一緒に飲酒をしたような事実があれば、知らなかったと言い逃れることは難しいでしょう。 -
(3)飲酒運転で事故を起こした場合
事故を起こしてしまうと、飲酒運転以上に厳しく罰せられます。
どの罪が適用されるのかは事故の状況によりますが、たとえば次の罪に問われるおそれがあります。- 過失運転致死傷罪……7年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 危険運転致傷罪……15年以下の懲役
- 危険運転致死罪……1年以上の有期懲役(最長20年の懲役)
行政処分については、前述した飲酒運転の処分に、被害者の負傷の程度による点数が加算されます。免許取り消しや免許停止処分となるほか、欠格期間が長くなる点にも注意が必要です。
このほか、民事上の賠償責任を求められるケースがあります。 -
(4)事故を起こして逃げた場合
事故を起こしたにもかかわらず、飲酒運転の発覚をおそれて逃亡すると「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」にも問われます。法定刑は「12年以下の懲役」です。
-
(5)呼気検査を拒否した場合
一斉検問などの際に警察官から呼び止められ、呼気検査を要求されることがあります。少量のアルコール摂取のケースなどは、なんとか飲酒の事実を隠したいと考えるかもしれませんが、呼気検査は拒否するだけで罪に問われることがあります。
「3か月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されます。
4、飲酒運転で後日逮捕されるおそれについて
飲酒運転をしてしまったが警察官に呼び止められることなく現に自宅に着いたのであれば、逮捕をしようにも、その時点ではアルコールが抜けていたりして、証拠の確保が難しいことから飲酒運転で逮捕されるのは現行犯逮捕が多いということになります。
しかし、すでに警察官から呼気検査などを受けていたなどの事情があれば、後に捜査のために呼び出されることがあります。素直に従っていれば行政処分で済むことも多いですが、呼び出しに応じない、逃走するなどすれば後日逮捕されることは考えられます。
事故を起こした場合には捜査がおこなわれ、自動車運転死傷処罰法違反の罪などで逮捕されるおそれもあります。
5、逮捕後の流れ
万が一後日逮捕されてしまった場合の逮捕後の流れを説明します。
飲酒運転で逮捕されると、逮捕後48時間以内に警察の取り調べがおこなわれ、その後送検され、送検後24時間以内に勾留請求がなされると、最長で20日間勾留されます。勾留されたら、多くの場合、勾留期間満了までに起訴・不起訴処分が決定されます。
起訴され裁判になると、事案によっては1年近くかかるケースもあります。
飲酒運転は人の命を脅かしかねない危険な行為であることから、厳しい結果が下されると心得ておきましょう。
逮捕された後は時間との勝負になります。少しでも量刑を軽くし、早期の身柄釈放を目指すためには、早めに弁護士に相談されるとよいでしょう。
6、飲酒運転の自動車保険適用について
最後に、飲酒運転で事故を起こした場合の保険適用についても触れておきます。飲酒運転をして人身事故や物損事故を起こしてしまった場合、何に対する補償がなされるかが問題です。
- 被害者への補償……被害者救済の観点から、相手方のケガや車の破損などに対する補償がおこなわれます。
- 自分自身への補償……飲酒運転は保険の免責事由に該当しますので、基本的に、加害者本人のケガや車の損害は補償されないことがほとんどです。
- 同乗者への補償……同乗者のケガなどに対する補償は原則おこなわれます。ただし、同乗者が運転者の飲酒の事実を知っていた場合には減額されることがあります。
7、まとめ
今回は、飲酒運転の処分や逮捕について解説しました。
悲惨な事故がなくならない現状を受け、社会的関心の高まりや、さらなる厳罰化の動きも考えられます。これまで以上に自己管理を徹底する必要があるでしょう。一度でも飲酒運転に身に覚えがあれば、今後は二度としないと心に誓ってください。
飲酒運転を行ってしまい逮捕された、あるいは逮捕におびえているのであれば弁護士に相談することが最善の方法といえるでしょう。後日逮捕の可能性や量刑の目安などを法的観点からアドバイスしてもらうことができます。
ベリーベスト法律事務所 金沢オフィスでもご相談をお受けします。飲酒運転をしてお困りであれば、一度ご連絡ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- |<
- 前
- 次
- >|