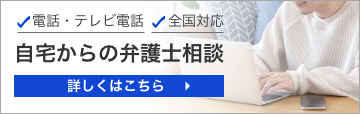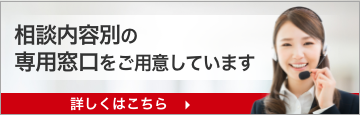リフォーム工事でトラブルが発生! 解決のための法的手続きを解説
- 一般民事
- リフォーム
- トラブル

長年所有している持ち家など、増改築や改修工事のリフォームを施す機会は少なくありません。
令和2年に総務省統計局が公表した平成30年住宅・土地統計調査結果によれば、金沢市を含む石川県において2014年以降に住宅の増改築・改修工事などが行われた割合は、県内の住宅全体の29.4%でした。
一方、業者にリフォームを依頼したところ、施工に不具合があった、見積書にない追加料金を請求された、工事の騒音で近隣から苦情が出たなどのトラブルになる場合もあります。
そこで今回は、リフォーム工事でトラブルが発生した場合の法的手続きの種類などを弁護士が解説していきます。
1、「リフォーム工事」関連で発生しがちなトラブルとは?
一般的にリフォーム工事で発生しがちなトラブルの事例についてご紹介します。
-
(1)施工の不具合によるトラブル
リフォームの施工の際に、不具合があることでトラブルが生じるケースです。たとえばリフォームを行った壁紙にはがれが生じた。あるいは屋根を葺(ふ)き替えたら雨染みが出てきた、設置した部品がしっかり固定されていないなどです。
また、当初の約束と異なる内容で工事をされるケースもあります。たとえば質の良い素材で工事を頼んだにもかかわらず、安価な資材を使用されたなどです。 -
(2)費用に関するトラブル
施工に問題がない場合でも、追加工事などで当初約束していた金額とは異なる費用をリフォーム会社に請求されたというトラブルもあります。
外壁の塗装費用の見積もりを出してもらって工事を依頼し、高所の塗装もしたほうがいいが足場が必要になるといわれて了承したところ、後日に足場の設置費用を追加請求されるなどです。
その他の費用に関するトラブルとしては、最終的な請求額が最初の見積もりと大幅に異なる、あるいは工事一式などの抽象的な記載で高額な費用を請求されるなどがあります。 -
(3)アフターフォローのトラブル
リフォーム工事がいったん完了して費用を支払った後、不具合が生じて業者に対応を依頼したところ、アフターフォローをきちんとしてくれなかったというトラブルです。
アフターフォローが充実しているといわれて契約したものの、保障の対象外とされて対応してくれない。あるいは、対応してくれても追加の費用をきっちり請求されるなどです。 -
(4)近隣とのトラブル
リフォームの施工や費用には問題がなくても、工事によって生じる騒音などで近隣住民とのトラブルが発生する場合があります。
近隣からいわれがちなクレームとしては、工事の騒音がうるさくて生活に支障をきたす、工事に使われる車両が邪魔で通行できない、工事の廃棄物や悪臭で環境が悪化する、リフォームによって隣家が日照不足になってしまったなどがあります。
2、「住宅関連」契約書類の基本
リフォームなどの住宅関連工事を業者に発注する際には、当然工事内容に関しての決まりごとを規定した契約が交わされます。その関連でもっとも重要な書類であるといえる「工事請負契約書」とその他の重要な書類について解説します。
-
(1)工事請負契約書とは
工事請負契約書とは、業者がリフォームなどの工事の実施を請け負うことを当事者間で合意した旨が記載された書面のことです。
リフォームについて何らかのトラブルが生じた場合、どのような内容で契約が締結されたかを示す契約書は重要です。締結した契約を書面にすることで、リフォームの注文者と工事を請け負う業者とがどのような内容で契約を締結したかが客観的に判断できるようになります。
工事請負契約書に決まった様式はありませんが、注文者と請負業者の情報、リフォームにかかる費用、工事の着工日と完成予定日、支払い方法などが記載されていることが重要ですので、必ず確認しましょう。 -
(2)工事請負契約書の関連書類
工事請負契約書はあくまで契約の概要を示したものであり、実際にどのようなリフォーム工事が行われたのかについては、他の書類の内容も重要になります。
リフォームの内容や規模によっては省略される場合もありますが、きちんと書類が作成されているほうが一般にトラブルの解決には役立ちます。
工事請負契約書に関連する重要書類としては、一般に以下のものがあります。
●見積書
リフォームの内容と工事にかかる費用を記した書類です。見積書の様式は業者によって異なりますが、重要な項目は合計金額、業者の名称、所在地、注文者の氏名、見積もり年月日、工事項目などです。
●工事請負契約約款
工事請負契約の詳細な内容をあらかじめ定型的に定めた書面のことです。契約書に表記するのは難しい詳細な事柄を記したもので、分量が多いのが特徴です。
内容は細かく記載され、リフォームについて争いが生じた場合は非常に重要な役割を果たす場合も少なくありません。
一般的な記載事項としては瑕疵担保の有無、遅延損害金のルール、不可抗力による損害の処理、第三者傷害の処理、近隣調整などがあります。
●仕上げ表
仕上げ表は、工事に使用する資材の種類や仕上げの方法などを記載した書類です。仕様書と呼ばれることもあります。リフォームにどのような資材をどのくらい使用したかなどを確認するのに役立ちます。
3、トラブル予防のための留意点
リフォームに関するトラブルを予防するために、発注先の業者とのやり取りなどを進める上で留意すべき点を解説していきます。
-
(1)必ず契約書を交わしておく
トラブルを防止するための第一歩として、規模の小さいリフォームであっても必ず業者と契約書を交わしておくことが基本です。たとえば知り合いの紹介などのよしみで口頭約束だけで工事を開始してもらった場合など、トラブル発生時に「いった、いわない」の水掛け論に終始しがちで、解決の糸口が見つからない事態に陥るからです。
また、契約書が存在しない場合、依頼した内容と実際の施工に差異があったとしても、当然どのような約束や合意があったかを証明することが非常に難しくなります。
万が一の事態に備えて、リフォームを依頼する際は契約書を交わすのが重要かつ基本原則であると心得ましょう。 -
(2)打ち合わせをしっかりと行う
リフォームの内容について、注文者と業者の間に認識のズレがある場合などにトラブルになることがあります。これらを回避するためにも、事前の打ち合わせをしっかり行うことが重要です。
まず、リフォームで実現したいことを洗い出しておいた上で、要望を明確に業者に伝えましょう。それでも疑問点が生まれれば曖昧にせず、質問しながら打ち合わせを進めれば、両者が認識している内容に乖離は生まれにくくなります。確認の意味でも、音声やノートにそれらの記録を残すことも有効です。 -
(3)できる限り証拠を残しておく
トラブル発生時に解決しやすくするためにも、リフォーム工事のさまざまな「証拠」を残しておきましょう。たとえば、工事の完了後も見積書や仕上げ表などの書類を保管しておく、リフォームの前後や施工中の様子を撮影しておくなどの方法があります。
リフォームの過程で変更があった場合は、変更内容を書面にしておくとトラブル防止に役立ちます。変更に伴って発生する費用を、発注者と業者のどちらが負担するのか明確にした上で、書面に記載しておくことも重要です。
4、リフォームトラブルを解決するための手続き
リフォームに関するトラブルが発生した場合、解決するためにどのような手続きを踏めばよいのか、その相談先や方法について説明します。
-
(1)各種機関への相談
リフォームに関するトラブルの相談に乗ってくれる各種機関として、「国民生活センター」や「住宅リフォーム紛争処理支援センター」があります。
「国民生活センター」は消費者庁が管轄する独立行政法人です。国民生活の安定および向上に寄与するために、国民生活に関する情報の提供や調査研究などを行っています。
全国に設置された消費生活センターを窓口として、住宅のリフォームを含む商品やサービスに関する苦情や問い合わせなどの相談対応を実施しています。
「住宅リフォーム紛争処理支援センター」は、国土交通省の所管する公益法人です。住宅の取得やリフォームに関する情報を提供するほか、住宅専門の相談窓口として「住まいるダイヤル」という電話相談サービスも実施しています。
リフォームの不具合などの電話相談、建築士によるリフォームの見積書のチェック、弁護士と建築士による対面相談などのサービスが用意されています。 -
(2)民事調停
「民事調停」は裁判所が関与する紛争解決の手続きの一種で、当事者同士が合意することで事案の解決を図るものです。リフォーム以外にも、債務の返済や家屋の明け渡しなどさまざまな事案に利用されます。
リフォームなどの建築関係の民事調停では、建築に関する紛争に詳しい弁護士や建築士などが立ち合い、専門家の知見を活用しながら解決への道を探る場合もあります。
民事調停のメリットは、当事者の合意のもとで法律に縛られずに柔軟な解決を目指せることです。調停が成立した場合は、合意した内容は訴訟における判決と同様の効力を有します。一方、当事者の双方が合意しなければ調停は成立しません。 -
(3)ADR
ADRとは「裁判外紛争処理手続き」の英語表記の略称です。訴訟手続きによらない紛争の解決方法全般を指すものです。前述した民事調停も厳密にはADRの一種です。
ADRの種類には、第三者が間に入って当事者の話し合いを進める「あっせん型」、民事調停を始めとする「調停型」、事前に当事者が仲裁を受けることに同意した後に、仲裁人が仲裁案を提示する「仲裁型」などがあります。
全国の弁護士会の中には、ADRの一種として住宅やリフォームに関する紛争の解決手続きを実施している団体もあります。「住宅紛争審査会」と呼ばれるもので、弁護士や建築士などの専門家によるあっせん、調停、仲裁などが行われています。 -
(4)訴訟手続き
民事裁判における訴訟手続きとは、裁判官が当事者の言い分を聞いたり証拠を調べたりした後に、判決をだすことで紛争の終局的な解決を図る手続きのことです。いわゆる裁判になります。
訴訟手続きの特徴は、当事者の合意がなくても紛争を解決できることです。民事調停を始めとするADRは当事者双方の合意が必要ですが、訴訟手続きは判決が確定すれば強制執行による権利の実現が可能です。
当事者の合意を要しないという強力な効果があるぶん、訴訟手続きは法律に基づいた厳格な手続きと判断が行われます。主張が認められるためには適切な法的主張や証拠集めなど、経験豊富な弁護士の力量も重要になってきます。
5、まとめ
住宅のリフォームは家屋の老朽化対策などに効果的な工事で、高齢化の進む国内では今後も多くのニーズが見込まれます。それに伴い、施工後の不具合や見積書にない追加料金などのトラブルが発生する割合も多くなるかもしれません。
リフォームのトラブル予防には、契約書を必ず交わす、打ち合わせを綿密に行うなど、商談における基本原則に沿って進めていくことがポイントになります。トラブルが発生した場合は、各種団体による相談サービス、民事調停、訴訟などの手続きで解決を図ることができます。
リフォームに関するトラブルでお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 金沢オフィスにご相談ください。住宅の法律問題の経験が豊富な弁護士が、解決に向けてサポートいたします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています